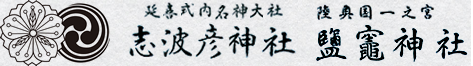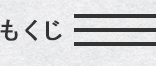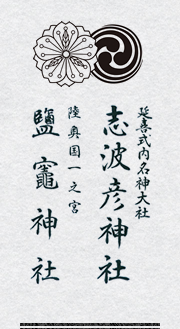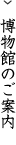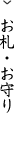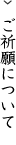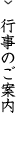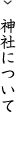藻塩焼神事並びに御釜神社例祭
来る7月6日(日)午前11時より、御釜神社例祭・藻塩焼神事を斎行します。
なお、調製しました「藻塩」は、祭典終了後、御釜神社社務所にてお頒ちいたします。

鹽竈神社の末社であり、鹽竈神社と同じ鹽土翁神を御祭神としてお祀りしております。
現在の御釜神社境内地周辺は、古来「甫出の浜」と呼ばれた浜辺で、御祭神により伝えられた製塩が行われた所と伝わっております。
芭蕉は塩竈に訪れた際、この御釜神社にも訪れ、神釜を拝したことが奥の細道に記されております。
塩竈の地名の由来は、こちらの御釜神社に伝わる神話によるものです。
四口の神釜
御釜神社には神釜と呼ばれる四口の鉄製の釜が祀られております。
この四口の釜は「日本三奇」の一つに数えられ、釜の中の水は溢れることも枯れることも無いとされ、江戸時代には変事ある時その前触れとして御釜の水が変わると言われました。
(神釜の拝観の際は初穂料100円をお納め頂きます)

宮城県無形民俗文化財 藻塩焼神事
七月四日・五日・六日鹽竈神社例祭に先立ち、塩竈市本町に鎮座する御釜神社において藻塩焼神事が斎行されます。
この神事は、御祭神・鹽土老翁神の製塩の故事にちなむもので、七月四日の藻刈神事、同五日の水替神事、同六日の藻塩焼神事の一連の神事で構成される特殊神事です。
藻刈神事(七月四日)
七ヶ浜花渕浜沖の海上に神事船を出し、ホンダワラと呼ばれる海藻を刈り採る神事です。
刈り採ったホンダワラは御釜神社に奉安されます。

御水替神事(七月五日)
御釜神社に奉安される四口の鉄製平釜は神釜と呼ばれ、鹽土老翁神が製塩に用いられたと伝えられています。神釜は常に水を湛えており、旱魃にも干上がることなく、世に異変がある時は変色などを示すとされています。年に一度、この水を汲み替える神事が水替神事で、神釜の水を汲み出したのち、松島湾釜ヶ渕に神事船を出して水を海中に返し、さらに満潮時の潮水を汲み帰って神釜を満たします。なお、汲み出した神釜の水は少量が取り置かれます。

藻塩焼神事(七月六日)
藻刈神事で刈り採ったホンダワラを竹棚に広げ、上から海水を注いで塩分濃度の高い塩水(鹹水)を得る所作を行ったのち、これを煎熬して塩を得る神事です。調製された塩は、御釜神社例祭・鹽竈神社例祭において御神前に供えられるほか、当日の参列者に御頒けいたします。
また、神事の最後には、前日に少量取り置かれた水が神釜に戻されます。この所作には、神釜の水の永続性を保つ重要な意味があります。